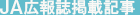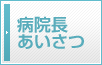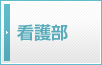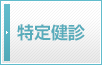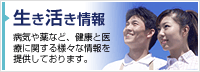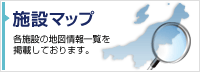ホーム > JA広報誌掲載記事 > 2021年11月号 感染制御チーム(ICT)
2021年11月号 感染制御チーム(ICT)
マスクの感染予防について
コロナ禍に入り一時は入手困難な事もあったマスクですが、今では色々な種類のマスクが入手できるようになりました。マスクの着用目的は、会話や咳などによる飛沫(しぶき)の飛散や吸い込みを防ぐこと。近年の研究では飛沫を出す側と吸い込む側、両者のマスクの着用状況やマスクの素材によって違いがあることが分かっています。スーパーコンピューター富岳のシミュレーションによるとマスクのフィルター性能は、布製やウレタン製よりも不織布素材を用いたほうが高いことが示されています。このようなフィルター性能の高いマスクは、装着した際に隙間ができるとそこから漏れが発生し性能が低下する為、これを防ぐために顔との隙間をできるだけなくすことが大切です。またマスクを二重にすることは、フィルター性能の低い布素材のマスク同士や、不織布マスクをゆるゆるの状態でつけた上に布やウレタンマスクをつけた場合などでは、ある程度の性能向上の期待はできますが、その効果は不織布マスク一枚を正しく付けた場合と大きく変わりません。また不織布マスクを二枚付けることは、空気抵抗の増加に伴い隙間からの漏れがより多くなってしまうのであまり意味がありません。不織布マスクをつける場合は、一枚をできるだけ隙間なく(鼻部分にワイヤーがある場合は顔の形に合わせて折り曲げるなど)顔にピッタリとフィットさせて装着することが大切です。
屋外ではマスクは不要?と思うかもしれませんが、河川敷でのバーベキューでクラスターの発生がみられたりもしています。屋外でも近距離で会話する場合にはマスクは必要です。マスクの感染予防にも限界はありますがその時の状況に合わせ可能な限りマスクを着用していくことが感染予防につながると考えます。