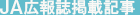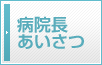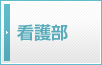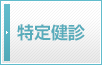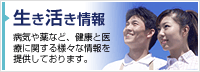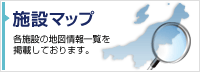ホーム > JA広報誌掲載記事 > 2018年 > 2018年10月号 副院長 津野吉裕
2018年10月号 副院長 津野吉裕
救急医療機関と救急車の適正利用のお願い
当院の救急診療体制が縮小され市民の皆様には多大なるご迷惑をおかけして久しくなり、大変申し訳ないと思っております。現在もまだ脳神経疾患と循環器疾患の急性期診療については、全面的に高次病院にお願いしている状態です。このような診療体制下での救急車の運行状況は必然的に遠距離搬送となることが多く、一旦出動すると長時間利用できないことになります。本来であれば最寄りの医療機関に搬送して短時間で帰署して待機する事が理想的ですが、重症患者さんの場合は当院での診療が制限されるため救急車は長時間利用できなくなります。また、自宅で亡くなった方の死亡診断のために救急車が利用されることもあります。
以上のことから、救急車の利用が最優先されるべき方のためにお願いがあります。
- ①定期的に通院して検査・治療を受けている医療機関(以下、かかりつけ医)がある方は、具合が悪くなった時に、まずかかりつけ医に相談する。
- ②末期癌患者様のご家族は生前に自宅での看取りが可能か、かかりつけ医に相談しておく。
- ③かかりつけ医のいない方は、具合が悪くなったら消防に電話してまず症状を説明する。休日診療所、救急指定病院など適切な医療機関の選定または搬送をお願いする。
- ④意識がない、痙攣している、顔色が悪い、呼吸がおかしい、怪我をして出血している、広範囲の火傷、吐血・下血、激しい嘔吐・下痢、半身まひ、溺れた、高所からの転落、等々はためらわず救急車を要請する。
- ⑤当院に通院中で具合が悪くなった方は、まず当院に連絡し日当直者に状況を説明してどうしらたいいか相談する。
- ⑥最近はスマートフォンの普及に伴い、「Q助」という救急受診の際に役立つアプリケーションソフトがあります。また、平成29年12月1日から始まった成人対象の電話による医療相談「#7119」ができるようになりました。小児は「#8000」で以前から活用されています。詳細は新潟県のホームページをご参照ください。