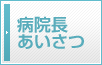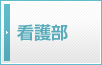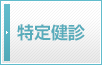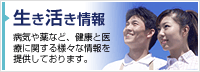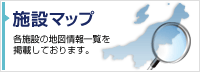ホーム > 学生実習記録
学生実習 新潟大学医学部医学科6年 遠藤柊哉
今年、2025年の7月7日より4週間、あがの市民病院で総合診療学の臨床実習をさせていただきました。お忙しい業務の合間を縫って毎日ご指導いただき、非常に実りのある実習となりました。私にとっては、この実習が学生としての最後の実習でもあり、節目として大変印象深いものとなりました。
思い返せば、5年次の初めに受けた十日町病院での総合診療実習から始まり、最後も同じく総合診療で締めくくるというのは、非常に感慨深いものがあります。あの頃と比べて、現場での立ち振る舞いや思考のスピードなど、自分の成長を実感することができました。あがの市民病院での実習は、そういった意味でも、この1年半の臨床実習の集大成と呼べるものでした。
私は、「自分の力が最も試される場」とは、人前に出るときだと考えています。指導医や上級医の前でプレゼンテーションをする場面、患者さんと1対1で問診・診察・説明を行う場面などが、その代表です。本実習では、まさにそうした場面を多く経験させていただき、1年前の自分からの成長をはっきりと感じることができました。もちろんまだまだ未熟な点はありますが、初期研修に向けて実りある学びを積むことができたと実感しております。
特に印象に残っているのは、夜間当直の見学です。さまざまな背景を抱えた患者さんが救急外来に訪れ、診断や治療だけでなく、帰宅や入院の判断、社会的背景への対応など、医学的知識以外の力も求められる現場を目の当たりにしました。こうした場面に柔軟に対応し、患者さん一人ひとりに向き合える姿勢と知識を、今後の研修を通じて身につけていきたいと強く感じました。
短い期間ではありましたが、実習を支えてくださったすべてのスタッフの皆さまに、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
学生実習 新潟大学医学部医学科3年 山下蒼路
私は3月17日にあがの市民病院で地域医療実習を行わせていただきました。そこで学んだことを、「地域医療の概念、地域医療病院の役割、リハビリテーションの役割」の3つに分けてここに書きたいと思います。
1つ、地域医療の概念について、医療とは、医療機関のみが提供するのでなく、福祉、介護、行政などの多くの方々の係りがあり実践されることを知りました。ここで、健康とは「身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態」であり、単に疾患が治るだけではなく、社会で、生活が安定してできることであると学びました。「地域医療」の概念は難しく、なかなか言い表せないのですが、英語ではcommunity/public health careと書き、この方がわかりやすい感じがしました。
2つ、地域医療病院の役割について、今回実習を行った あがの市民病院は、地域中核病院であり、大学病院や基幹病院とは異なる役割を持っています。大学病院や基幹病院などでは、急性期の疾患の治療に焦点を当てていて、「疾患を治す(cure)」場所です。地域中核病院では、在宅を見据えて、治療後の「リハビリテーション」「退院支援」などの「ケア(care)」を行います。両者は、車の両輪の関係です。つまり、地域中核病院は、単なる医療のみでなく、福祉、介護、生活の視点をも持った病院といえます。
3つ、リハビリテーションの役割について、リハビリテーションには理学療法、作業療法、言語聴覚療法の3種類が存在し、それぞれ、運動機能の回復、日常生活機能の回復、言語・聴覚・摂食機能の回復などの役割を担っています。リハビリテーションは患者さんが社会復帰できるように支援します。患者さんが「治療してよかった」と思っていただけるよう、高齢化社会では特に大切になってくると感じました。
私が医師を志望した理由は、「自分の周りの方々を、安心させる存在になりたい」です。病気の治療法そのものに強く興味があったのですが、今回、地域医療の重要性を知ることができました。今回の実習で、地域医療について考える機会をいただき、良かったと思っています。
今回の実習を指導してくださった先生方に、感謝申し上げます。
学生実習 日本大学1年 角田海翔
本日は、あがの市民病院での病院実習を通して、貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。
今回は主に、病院内の施設と実際に行っている診療、入院した患者さん,退院する患者さんへの対応などを見学させていただきました。
その中で、初めて透析治療を見学することができ、治療器具の詳しい説明や、何を行うための治療なのかなどを教えてもらい、どのようにして血液を循環させ、正常な値にしていくのかを理解でき、とても有意義な時間になったと感じました。一人当たりの治療に対してかかる費用や資源の量などを知り、とても驚きました。
また、退院する患者さんのカンファレンスにも参加させていただいたのですが、様々な職種の方々が集まり、意見を交換し合って今後の方針などについて話し合っている様子から、チーム医療というものを肌で実感することができました。そして、患者さんの訪問診療などについてのお話もあり、地域との密接な関わり合いを感じることができました。その地域の特性や需要に合った形で医療を提供していくことが、地域医療として大切なことではないかと感じました。また、病院内だけではなく、病院同士のつながりも患者さんを救うためには必要不可欠であると感じました。
今回の実習では、初めての体験も多くあり、難しい内容のこともありましたが、自分に必要な能力などを伸ばし、成長していきたいと考えています。
あがの市民病院 早期医学体験実習 新潟大学医学部1年 佐藤覇也
1日目
8月20日の午前にリハビリテーションの見学をさせていただきました。はじめに理学療法士による、帯状疱疹の患者さんへのリハビリを見学させていただきました。脚を中心にストレッチしてから歩行器で歩く練習をするという内容で、帯状疱疹によってまだ食欲に影響があるとのことでした。そして、COPDの患者さんのリハビリを見学をさせていただきました。ベッドでの脚のリハビリで、筋肉や関節をほぐすことで少しでも楽になってもらうために行っているとのことでした。次に作業療法士の方と右手首を骨折された患者さんのリハビリを見学させていただきました。その患者さんがされている仕事の動きを想定したリハビリを行っていました。最後に言語聴覚士の方と失語症、失行の患者さんのリハビリを見学させていただき、日常的なコミュニケーションができることを目標にしたリハビリでした。そして、脳梗塞の患者さんのもとにも行かせていただきました。
リハビリテーションの見学をして思ったのは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の方々は、単に患者さんの症状だけに着目しているわけではなく、患者さんが元の生活ができるように、個々に合わせたリハビリを行っているということでした。
午後はまず介護医療院と五頭の里を見学させていただきました。両者ともに女性の比率が高い印象を受けました。また、看護師、介護士の方々が役割を分担し、施設の方々がよりよく暮らせるように努力されている姿を拝見することが出来ました。最後に回診に同行させていただきました。まだ医学的知識が浅いが故に、医師、研修医の先生方が話されている内容を一部しか理解することはできませんでしたが、医学部に入ったばかりで回診に同行する機会をいただけて、今後の医学を学ぶ上でのモチベーションが大いに向上しました。
貴重な機会をいただき大変感謝しております。
2日目
8月21日の午前は、検査科及び薬剤部の見学をさせていただきました。まず検査科では血液検査や尿検査、エコー検査などの見学をさせていただきました。今まで検査科の現場に行ったことがなく、検査科の仕事に対してなんとなくのイメージしかありませんでした。しかし、各検査の説明等を丁寧にしていただいたので、まだ勉強していない内容が多く含まれていたとはいえ、よりはっきりとしたイメージをもつことが出来ました。次に薬剤部の見学をさせていただきました。錠剤や粉薬、注射が陳列しているのを遠目でしか見たことがなかったので、間近で見る機会を頂けて良かったです。また、薬剤の取り違えがないようにバーコードで管理しているのも確認することができました。検査科、薬剤部ともに医師と密接に関連しており、将来、より良いチーム医療を展開するうえで、これらの現場を1年生の段階で知ることができたことに感謝しております。
午後は訪問看護に同行させていただきました。一人目の方は糖尿病、二人目の方は認知症でした。看護師の方がどちらの方に対してもコミュニケーションを通して健康状態を確認していたのが特にすごいと感じました。
次に内科の検討会に参加させていただきました。そこでは医師になってからも学び続ける大切さを学ぶことが出来ました。
3日目
8月22日の午前に内科の外来と放射線科を見学をさせていただきました。
まずは内科外来で腎臓の疾患を持つ方を中心に見学させていただきました。今
までは、外来は患者側でしか経験したことが無かったため、医師が外来をどのような一連の流れで行なっているかを学ぶことが出来ました。また、患者さんとのコミュニケーションを大切にしつつ、待っている患者さんのことも考えていらっしゃると思いました。そして、初めて聴診器を実際の患者さんに当ててみるという機会を1年生の段階でいただき感謝しております。
次に放射線科の見学をさせていただきました。放射線を扱う機械をいくつか見学をさせてもらいました。画像を多く扱うことから、パソコンの数が他の場所よりも多いと思いました。様々な機械があり、あがの市民病院が地域を代表する病院であることがわかりました。また、放射線科で得られた画像等をもとに医師が診断するのだという、将来医師になるうえでのイメージも持つことが出来ました。放射線を扱うそれぞれの機械の違いを分かりやすく教えていただき感謝しております。
あがの市民病院 早期医学体験実習 新潟大学医学部1年 田中秀摩
1日目
午前中の実習ではOTさん、PTさん、STさんが、実際に患者さんにリハビリテーションを行っている様子を見学させていただいた。
PTさんの行った主な内容は、下肢のストレッチおよび運動と歩行器を用いた歩行訓練であり、一区切りついたタイミングで血圧測定を行っていた。逐一患者さんの様子を伺いながら無理のない範囲でリハビリを行なっていた様子や、仰臥位から座位になるタイミングで患者さんの様子に変化がないかを確認しつつリハビリを行っていたのが印象的であった。COPDで治療中の別の患者さんのベッドサイドでのリハビリも見学させていただき、リハビリ中に、SpO2に注意を向けながら酸素量を調整しつつ、この方に対しても無理のないリハビリを行っていたのが印象的であった。
続いてOTさんのリハビリの様子を見学させていただいた。手首を骨折して2か月ほど経過し、リハビリで機能回復が見られていた患者さんであり、日常想定される作業を想定し、負荷をかけながらのリハビリを行っていた。患者さん本人も、リハビリを通して骨折してから回復してきている様子を自覚しているようであり、OTさんもその患者さんの自信をさらに持ってもらうための声掛けを行っていたのが印象的であった。
最後にSTさんのリハビリの様子を見学させていただいた。失語の方の発話訓練を行う様子を主に見学した。STさんに関しても患者さんがしっかりと発音できたことに対して労いの言葉をかけつつ、患者さんのペースに合わせたリハビリを行っている印象であった。
いずれのリハビリでも共通していたのは、患者さんのペースに合わせつつ、体調の変化がないかをしっかりと確認しながら、リハビリを行っており、患者さんが出来たことに対して以前よりもできることが増えているということを自覚してもらえるような声掛けをしていたという点であり、医療者として患者さんに関わる中での重要なことの一つを学ぶことが出来た。
午後の実習では介護医療院および五頭の里の見学をさせていただいた。両者はいわゆる介護施設として多くの利用者のケアを行っているが、両者の雰囲気の差がまず印象的であった。介護医療院では継続的な医学管理が必要な方がいるということもありかなり静かな雰囲気であったが、五頭の里はADLが高い方が多いため、歌謡曲がBGMで流れていたり、利用者同士でお話しされていたりしていて、とても賑やかな雰囲気であった。両者とも医師、看護師、介護士などの方々が連携し合いながら利用者の方のケアを日常的に行っている様子を見学させていただき、新潟、 特に阿賀野地域においての高齢者ケアにおいて大きな役割を果たしている施設であるということを実感した。
最後に病棟回診に参加させていただいた。担当の先生方が簡潔にその患者のこれまでの経過、現状、今後の方針について簡潔にまとめてプレゼンテーションされおり、しかもその内容も分かりやすく感じ、とても印象的であった。しっかりと患者に向き合い、その患者への対応などについてまとめたからこそのプレゼンテーションであったと感じた。
2日目
午前中は薬剤部と検査部の見学をさせていただいた。薬剤部では、朝から外来の患者さんの院外処方や入院患者の院内処方の対応を多く行う必要があったためか、多くの薬剤の準備がなされていた。準備した薬剤が、本当に間違っていないか、医師の指示に疑問点はないか、などの確認を普段から行っているとのことで、薬剤師の皆さまは、日々ご多忙の様子であった。その中でミスをしないようなシステムを構築して作業を行われている様子を見ることが出来、将来医師として、薬剤の処方を行なう際には適切な指示を心掛けなければならないと感じた。次に検査科では様々な検査について説明をしていただきながら、実際に検査している血液や喀痰培養などを顕微鏡で覗かせてもらった。その様子から、何がわかるかなどはまだ知識が乏しいためわからなかったが、患者さんの治療には、このような検査を多く行っている技師さんの存在が必要不可欠であり、まさにチーム医療の一部であると感じた。
午後には訪問看護に同行させていただき、看護師と利用者さんのやり取りを見学した。最初は利用者さんの体調に変化がなかったか、何か困っている点はないかなどの健康面でのお話をされていたが、それだけではなく、日常的な会話も交えており、コミュニケーションを重視している様子も見ることが出来、医療においてコミュニケーションの重要性を改めて実感した。自宅でのケアをされていた奥様に対しても、ねぎらいの言葉をかけつつ、ご家族のご様子も伺っていたので、訪問看護では、利用者の健康管理だけでなく、その方を支えるご家族へのケアをすることも、重要な役割の一つであると感じた。
最後に内科の症例検討の様子も見させていただいた。研修医の先生が以前担当されていた患者さんの事例を話されていたが、まだ知識が乏しく、難しいことも多かったが、今後は自分もその内容をしっかりと理解できるような勉強をしていかなくてはならないと思うと、学習に対するモチベーションが上がったように思う。
本日も多くのスタッフの方々がご多忙の中で、貴重な経験をさせていただき、今後医学生として過ごしていくモチベーションが上げることができた一日であると感じました。
3日目
本日は最初に放射線科にて放射線技師の方から行われている検査についてお話を伺いつつ、実際に患者さんを撮影している様子を見学させていただいた。朝から外来で検査をする患者さんが多くいらしていたため、とてもお忙しそうにしていたのが印象的であった。また、この科にある様々な検査機械についても丁寧に説明していただいた。あがの市民病院は、阿賀野市の中核病院であるため、設備の整った病院であるということを感じた。それでも検査が出来ない場合には、他の医療機関とも連携をしているとのお話も伺ったので、地域医療を支える病院として、他の施設と連携を密にとり、患者さんに対応しているこ
とを理解することが出来た。
ついで外来での診察の様子を見学させていただいた。腎臓内科の外来であったため、多くがCKDで通院されている方であった。診察時にはこれまでの経過を確認してもらうために、採血データを見せながら、現状についての説明を分かりやすい言葉でされていた。受診している患者さんのほとんどが高齢者であるため、わかりやすく簡潔に伝える能力が医師として非常に大事であるということを実感した。また、シャントを増設し、今後血液透析を行う方のシャントのスリル音を確認したり、実際にシャント音を聴診させていただいたりした。シャントの観察は今までしたことが無かったので、とてもいい経験が出来た。
令和6年度実習 順天堂大学医学部3年 吉岡原平
本日は、新潟県地域医療夏季実習として、あがの市民病院で実習をさせていただきました。まず初めに、地域医療について考えるにあたって、病院長の藤森先生からお話を頂きました。少子高齢化が進む社会において、「少ない医療資源の中で、地域でいかに支え合っていただくべきか」について思いを巡らせる機会となりました。また、住み慣れた地域で患者さんがその人らしい生活を送るためにできることを考えながら、医療を提供することの重要性を認識し、「地域包括ケア」の意義について学びました。
午前中は、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士さんによるリハビリの様子を見学させていただきました。それぞれの患者さんへの関わり方で印象に残った点は、リハビリの中で患者さんと多くの言葉を交わし、返答の中から患者さんのこれまでの生活背景を探る、あるいは退院後に不安に思うことを挙げてもらうなど、具体的なイメージを持ちながら行うリハビリを決めていた点です。作業療法士さんがおっしゃっていましたが、その人にとって「最も大切にしたい作業」は何かを考えてリハビリを行う、ということは、まさしくその人がその人らしい暮らしを行うことにつながると感じました。
午後には訪問看護に同行させていただきました。看護師さんによるバイタル測定や清拭、介護されている家族の方とのコミュニケーションの様子を見学させていただきました。在宅での医療は、訪問看護師以外にも医師や介護士などが介入するため、それぞれが感じ取った様子や患者さんの状態などを記載したメモを冊子にして細やかな情報共有を行っていました。在宅での医療提供は、より患者さんの生活様式に合わせたケアを提供できる場であると感じると同時に、医療従事者と患者さん、さらには患者さんの周囲の方々との信頼関係が非常に大切であると感じました。
地域に暮らす方々の不安に耳を傾け、地域全体が健康的な生活を送ることが出来るように見守り、支えられる医師になるために何が必要なのかを、今一度考え、今後に生かしていきたいと思います。
この度は大変貴重な機会を頂きまして、ありがとうございました。
令和6年度実習 杏林大学医学部3年 寒河江もなみ
私は今回、検査科での臨床検査体験と訪問看護への同行をさせていただきました。午前の臨床検査体験ではエコー検査の見学やグラム染色、血液検査の体験、病理検査の見学など他にも様々な体験、見学をさせていただきました。腹部のエコー検査の見学では、先生が検査に使うゼリーが冷たいことや、検査で当てる器具がぶるぶると震える(肝硬度測定)ことなどを、患者さんに声掛けを行い、患者さんの様子を見ながら検査を進めている姿が印象的でした。撮影技術や患者さんへの配慮が無ければ良い検査とは言えないのだと学びました。
また、病理検査の見学では患者さんの身体から得た組織や細胞からどのようにして病理標本を作製するのかを見させていただきました。血液検査や尿検査の解析の多くが機器を使っているのに対し、標本にする作業は多くが手作業で行われており、とても繊細でした。特にスライスして皺のよった組織は4㎛の厚さであり、それを水の表面張力を使って広げると聞いたときは、実際にその作業を見学できたわけではありませんが、想像しただけで息を飲むような作業だと感じました。
午後は訪問看護に同行させていただきました。患者さんの居住環境を実際にみて確認することで、病院では気づくことのできない、本来の患者さんの様子に気づけるのだと分かりました。また、看護師の方の記録には、その日話した雑談も書かれており、雑談から患者さんの生活の様子を良く知る鍵になることがあることを知りました。
日本社会、医療界の問題として、「高齢化」があります。「高齢者の認知機能の低下」や「高齢者夫婦世帯・単身世帯増加」の問題があることを学習しました。「高齢者が最後まで住み慣れた自宅で過ごしていく」ためにどうすればよいか、解決するのは大変難しいと思います。解決策の一つとして、患者さんが病気にかからないようにする予防医療が挙げられました。特に患者さん自身が意識することで行なえる禁煙やポピュレーションアプローチとなる健康診断などは効果的なのではないかと感じました。現在の高齢化率が約36%である阿賀野市では、これらの問題に対して住民、行政、医療者が協力して行う「地域包括ケアシステム」を展開しています。
私が将来、地域医療を担うにあたって、これからは自分のことだけでなく「地域社会を成り立たせるための医療とはどういうものなのか」を考えていくべきことを学びました。
最後に、この度はお忙しい中、多くのことを教えてくださったあがの市民病院の皆さま、ありがとうございました。今実習で学習したことを心に留め、今後も精進していきたいと思います。
令和6年度実習 新潟大学医学部3年 山中拓哉
2024.8.9本日は地域枠夏季実習にてあがの市民病院様に一日お世話になりました。
本記録では午前中にお伺いした生理検査と午後からの訪問診療及び講義に関する感想を記述いたします。
まず生理検査ではエコー検査による診断を2件間近で観察させていただき、担当の先生より臓器の見え方や画像の所見等について教えていただきました。大学では人形を用いた簡単なエコー検査について学習済みであったため、ある程度は分かったようなつもりでいたのですが、実際に先生が患者さんを診る際には私の知っているものよりもはるかに複雑に見える機器を繰っており、臨床でエコーによる検査を行うことが想像していたよりも難しいことがわかりました。
その後は、患者さんの検体から細菌のグラム染色の体験をさせていただきました。3年の前期で細菌学の授業を履修したばかりということもあり、その知識の復習も兼ねながら楽しく取り組ませていただきました。
グラム染色と観察の後に、患者さんの血液の検査を行っている場を見学させていただきました。検査項目の異なる検体をすべてその一角で捌くとなると大変な労力が必要になると思っておりましたが、現場では試験管のバーコードの読み取り、機械に通して結果をコンピューターで確認できるようになっていました。先ほどのエコーの件も含めて、医療の現場ではこうした専門的な機器を自身の手足のように取り扱えるだけのスキルが必要とされているということを改めて実感いたしました。
最後は病理生検を作っていらっしゃる方にお話を伺いました。大学の組織学や病理学の授業で扱うような生検が如何にして作られているのかを懇切丁寧に教えていただきました。
病理生検を一つ作るだけでもその工程は多く、制作におおよそ3日係ると聞き、想像していたよりも大変な仕事であることが分かりました。また、生検を作るだけではその仕事は務まらず、病理診断について臓器別に詳しい知識を有しておく必要があることにも驚かされました。
今回の実習の前半で生理検査が病の診断において、どれほど重要な役割を担っているか身をもって感じることが出来ました。
午後からは訪問診療に同行させていただきました。これまで病院見学は経験があっても訪問診療については知識がなく、その様子をイメージすることしかできませんでした。
今回同行させていただいた経験を通して、高齢者が多い地域における訪問診療のニーズの高さと訪問診療を行う際の地域住民からの信頼度の重要さを強く感じました。
講義で聞いたように新潟県では面積当たりの医療機関が少ないだけでなく、冬場は積雪の影響もあるため、疾病のある高齢の患者さんにとっては訪問診療がかなり重要であることが分かります。また、実際に同行することで、訪問診療はその地域住民から医療者への厚い信頼があって初めて成立するものだと感じ、地域と一体となった医療の実現のために平素から患者さんに安心していただけるような振る舞いを意識していきたいと考えました。
そのためにもまず自分が今できることとして、大学での講義内容を再度復習するなど確かな知識を身に着けていくことに努めたいと思います。
本日はご多忙の中お時間を割いてくださいました院長並びにスタッフの方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。
令和6年度実習 新潟大学医学部3年 江田裕貴
私は今回リハビリの様子を見させていただきました。今までに見学した病院では、医師や看護師の様子を見てきたので、とても新鮮でした。理学療法士さんが患者さんの様子を的確に判断してリハビリや治療に繋げていく様子がよくわかりました。患者さんとの心理的な距離がとても近く、やはり医師や看護師とも違う感じがありました。特に印象に残ったことは理学療法士の方が患者さんに患部の具合など、何度も質問していたことです。足の曲げ伸ばしによる筋肉や関節の痛み、違和感を聞くだけでなく、前日との感触の違いやどういう違和感なのか、治療の進捗などを詳しく聞いていました。このように患者さんから詳しく情報を集めることが、その後のリハビリの方針を決め、患者さんのためになっていくのだなと思いました。併せて、小さなコミュニケーションの積み重ねが患者さんと理学療法士さんの信頼関係の構築にも繋がるのだと考えました。他にも言語聴覚士の方が実際に患者さんの喉に触れて嚥下の状態を確認していた様子も印象に残りました。
地域医療においても各医療従事者と患者さんとの距離感や信頼関係は重要なことだと私は考えています。阿賀野市は、高齢者をケアする施設の数や支援の体制の点で比較的充実している一方で、開業医の少なさや高齢化も進んでいる現状もあると教えていただきました。そういった中で医療従事者の一員である理学療法士の方の一生懸命な様子を見学させていただき、とても感銘を受けました。また、本日は訪問診療にも同行させていただきました。在宅医療という形式上、毎日患者さんの様子を見ることはできません。そこで患者さんと適切にコミュニケーションをとりながら小さな変化や療養の環境にも目を向けることが大切だと分かりました。患者さんの家族からも情報を集めていたことも印象に残りました。考えていたよりも訪問診療を行う医師の大切さを感じました。自分が将来医師になった時の患者さんとの距離感や信頼関係を今から考えていきたいなと思いましたし、こうした小さなことの一つ一つが地域医療にもつながっていくのだと思いました。
令和6年度実習 新潟大学医学部6年 澄川航司郎
7月25日までの総合診療科病院実習に於きまして大変良くして頂きましたこと、心よりお礼申し上げます。
病院実習では、初日の体調不良もありご迷惑をお掛け致しました。初日は緊張もありましたが七夕コンサートにも参加させて頂き、地域の患者さん達との密な交流を図ることができ、4週間の実習を充実したものとさせる事ができました。担当患者の受け持ち、外来実習、訪問診療、リハビリテーション、臨床検査実習、当直への参加など、地域の中核病院としての仕事を幅広く学ばせていただき、将来地域診療に参加し一端を担う医師になれるよう心意気を新たにしました。医師国家試験に向けて益々邁進し、より一層自己研鑽に励んで参ります。
末筆になりますが、あがの市民病院の皆様方のご健勝をお祈り申し上げます。
令和6年度実習 新潟大学医学部6年 白坂菜乃花
この度は4週間、あがの市民病院にて総合診療学の実習をさせていただきました。実習期間中は、主に外来実習と病棟実習をいたしました。
外来実習では問診から診断、そしてその後の方針を立てて薬を処方し、入院することになった患者さんに関しては、入院の計画を立てるところまでを先生方の助けを頂きながら行いました。
病棟実習では入院している患者さんのところに回診に伺ったり、検査結果を都度確認したりして、普段先生方が行っている病棟管理について学習させていただきました。また、回診や症例検討会で、自らプレゼンテーションさせていただきました。
どちらもただ見学するのではなく、実践的に学ばせていただき、非常に貴重な経験となりました。
これらの他に、検査実習や訪問診療、リハビリ実習、当直の見学など様々なことをさせていただき、4週間という短い期間であったにも関わらず非常に学びの多い時間を過ごすことができました。
今回の経験を糧に、これからもより良い医師にとなれるよう精進して参りたいと思います。
最後に、お忙しい中ご指導いただいた先生方、メディカルスタッフの方々、事務の方々に、厚く御礼申し上げます。本当にお世話になりました。
令和6年度実習 新潟大学医学部6年 菅原広輝
1か月という短い期間でしたが、内容の濃い実習をさせて頂き、ありがとうございました。
急性期の治療から始まり、退院後のことまで考えて、医療と介護、福祉が連携して患者さんをサポートすることの重要性を学ぶことができました。そして訪問診療やリハビリなど、幅広い分野を学ぶことができました。
また、外来では問診、診療から検査や処方のオーダー、結果説明や再診までさせて頂き、診療を最後まで一貫して行う初めての経験になりました。
また、検査科での実習も今後検査をオーダーする時に役立つ知識が多く、有意義な時間となりました。
お世話になった方々が皆様親切で熱心に指導して頂き、充実した実習になりました。この1か月で学んだことを今後の医師人生でも活かしていきたいと思います。
大変お世話になりました。
令和5年度 地域医療研修 落合薫
「地域医療」とは
地域医療とは、地域にある総合病院や、個人医療施設、介護施設などの医療機関が連携し、提供されている医療である。連携し患者のデータを地域内で共有できるという点や、一人一人をしっかりとサポートできるといった良い点がある。一方で医師不足により、提供できない医療分野があるなどの課題が見られる。
目指す医師像
・医学に精通し、高い技術と豊富な知識を持つ医師
・患者の立場や視点を重視することが出来る医師
・患者やその家族から信頼されるような医師
感想
本日は貴重な体験をさせていただき、自分にとって、大きな財産となりました。病院の中を見学させていただいたり、訪問診療に同行させていただいたことは、初めての体験であり、学ぶことが多くありました。また、リハビリを見学させていただき、患者さんとコミュニケーションをとることが出来ましたが、患者さんの生の声を聴くことは、非常に良い経験となりました。また、地域医療とは、医療過疎地域で行う医療であると考えていましたが、それだけではなく、患者の方に寄り添い、その上で医療を提供することが大切であると学ぶことができました。
今回経験させていただいたことを忘れず、自分の目指す医師像に少しでも近づけるよう、精進していきたいと思います。
令和5年度 地域医療研修 関沙帆子
「地域医療」とは
・病院に来ている患者さんのその瞬間だけを見るのではなく、その人の生活や家族までを知り、サポートする医療。
・患者さんの病気や生活を知るためにもコミュニケーション能力がより必要となる医療。
・医師だけでなく、他の医療従事者と協力して地域全体を支える医療。
・患者さんの病気の予防を手助けする医療。
目指す「医師像」
・技術と知識を十分に持ち、患者さんだけでなく、一緒に働く医療従事者からも信頼される医師。
・コミュニケーションを多くとり、患者さんの口調や表情から、ささいなことにも気づけるような医師。
・地域医療で活躍できるような、患者の気持ちを理解し、寄り添う医師。
感想
実際に訪問診療に同行して、ただ患者さんの様子を見るだけでなく、患者さんの住んでる環境や食事の様子などにも気をかける必要があることがわかりました。
検査室での実習では、大学の実習でやったことがあるグラム染色や顕微鏡観察の知識や技術を生かして、その応用などを行い、とても貴重な体験ができました。
地域では医師不足が重大な問題にもなっているので、まず住民・県民が病気にかからないために予防医療が重要なこと、各自の自己管理が必要であることがわかりました。患者さんが自己管理できるために医師として助言したり手助けしたりする、地域包括ケアに係ることが、地域医療の一つであることを学びました。
大学で授業を受けるだけではできない体験ができ、有意義な時間となりました。
ありがとうございました。
令和5年度実習 新潟大学医学部6年 新嘉喜武
この度は4週間、あがの市民病院で総合診療学の実習をさせていただきました。大学での実習ではできなかったことを数多く経験することができ、実習に参加できて本当に良かったと思っています。
外来実習では実際に当院を受診された患者さんを診察させていただき、自分で問診し、身体診察を行い、鑑別疾患を挙げ、検査のオーダーを考え、そこで判明した検査結果を踏まえて、追加の問診を行い、最終診断を考え処方を行いました。今まで紙の上だけにあった医学知識を実際に応用でき、非常に勉強になりました。診察が終わっても、あの診断は本当に正しかったのか、もっとすべき問診や考えるべき鑑別疾患があったのではないかと何度も反芻し、自分に足りない知識や技術を再確認する機会になりました。一人の患者さんから学べることは膨大で、私たちは患者さんに勉強させてもらっているのだということを改めて認識することができました。
また病棟では何人かの患者さんを担当させていただき、毎日診察するなどコロナ禍ではなかなか経験できなかった病棟管理について学ばせていただきました。実際、患者様とどのようなことをお話するのか、どういったふうに感じているのかなど考え・学ぶことが数多くありました。大学での実習よりも、一人の患者さんにより多くの時間を使うことができ、その患者さんが入院した背景やこれからの病状を踏まえて、どのような声かけを行うのが適切なのかなど、臨床での難しさを実感しました。
その他にも、リハビリテーションや臨床検査など私たちがオーダーを出した先でどのようなことが行われているのかを見学させていただくこともできました。リハビリでは一つ一つの動作がどの部位に働くかなど綿密に考えられており、また患者さんと接する時間が長く色々な世間話をして患者さんとコミュニケーションを取り、単に身体機能の回復だけではない様々な役割を担っていると感じました。臨床検査では私たちが診察して出したオーダーが、どのように行われているのかを見ることができました。血液培養1つを取っても様々な工程を経て行われており、そこには技師の方の卓越した技術が必要だということを実感しました。オーダーを出すとすぐ返ってくる状況は当たり前ではなく、周りのスタッフに支えられて初めて実現することなのだと改めて認識しました。
今回の実習は院長や指導医の先生方をはじめ、さまざまな方々に支えられて、とても有意義なものとなりました。これからも良い医師になれるように精進してまいります。
本当にありがとうございました。
令和4年度実習 新潟大学医学部6年 佐藤諒汰朗
あがの市民病院にて3週間、総合診療学の実習をさせていただきました。どの病院スタッフの方々も温かく、学びやすい環境を作ってくださりありがとうございました。
指導医の先生のもと、診察から検査・処方のオーダーまでの一連の流れを考える外来実習は、学びの連続でした。最初に得た学びは、当たり前のことなのですが、診察室という場所において1人で考え込む訳にはいかないというものです。時間をかけて鑑別疾患を考えることは今までに経験を積んできましたが、問診や身体診察の事項、患者さんの今の困り具合やご希望など、様々な要素を頭の中でリアルタイムに考えながらの診察はほとんど経験がなく、その難しさを感じました。
また、診察以外にも検査科であったり内視鏡室であったりと、様々なことを見学、体験させていただきました。1つの診断に至るまでに多くの人の深い経験と知識が関わっているということを実感するもので、そのどれもが有意義な経験となりました。
今回の実習で得た学びを踏まえて、よりよい医師となれるよう、これからも精進して参ります。
令和4年度実習 新潟大学医学部6年 小宮隆弘
4月4日から3週間あがの市民病院で総合診療学の臨床実習をさせて頂きました。
外来実習では問診や身体診察を行うことができました。初診外来を担当させていただいたのは初めてであり、必要な検査を考えながら行う外来診療の面白さを感じることができました。しかし、その反面、患者さんに伝わる言葉選びが難しく、身体診察の技術が未熟であることを痛感する場面もありました。
病棟では3人の受け持ち患者さんを持たせていただきました。指導医の先生方が親身になり教えてくださったことで病態から深く考えることができました。
検査科実習では、グラム染色、CDI検査、ABO血液型判定検査、尿沈渣検鏡、呼吸機能検査、病理の切り出しなどを行うことができました。
その結果、外来診療でオーダーを出す時に、検査科の方々の仕事をイメージしながらオーダーを出すことができるようになりました。
お忙しい中、学生のために時間を割いてくださったスタッフの皆さまと患者さんの一人一人のご協力により実りのある実習を行うことができました。感謝を申し上げます。
令和3年度実習 新潟大学医学部6年 早川陽太
一ヵ月ものあいだ、大変お世話になりました。外来はもちろんのこと臨床検査や内視鏡、病棟、救急外来など様々な所でご指導を頂き、充実した時間を過ごすことが出来ました。ありがとうございました。
最初、外来では、患者さんとどう話せばよいのかや、鑑別診断・検査内容も十分にわからないような状況で、自身の勉強不足を痛感いたしました。その中で優しくアドバイスをして下さった榎本先生や、振り返りの中で臨床に対する感覚や思考の働かせ方を教えて下さった藤森先生のおかげで、まだまだ至らないながらも、成長することが出来たと思います。
臨床検査では、実際に解釈の仕方の指導を受けながら見学させて頂きました。加えて、患者さんにエコーや心電図を行う実習をさせて頂き、大変勉強になりました。
事務の方々にも本当に良くして頂き、実習全体を快適に過ごすことができました。
皆様、誠にありがとうございました。
令和元年度実習 新潟大学医学部4年 本間純
今回、あがの市民病院での実習ではいろいろなお話を聞かせていただき、また、貴重な体験をさせていただきました。
あがの市民病院はこの地域の患者さんの急性期から回復期、慢性期に至るまですべての医療を行っており、地域医療ならではのものを見学することが出来ました。在宅医療も行っており、高齢化が進む日本においてこのような医療はとても大切なのだと感じることが出来ました。患者さんの病気だけを見るのではなく、その背景にも目を当てて、患者さんの生活を考えた医療がなされていました。
午前中にはリハビリ、臨床検査、薬剤部を見学させていただきました。ふだんあまり見ることがなく、有意義な時間となりました。リハビリ部門ではリハビリの様子を見るだけでなくリハビリの理念とその重要性を教えていただきました。臨床検査部では、血液検査、エコー検査、呼吸機能検査の様子などを見させていただきました。検査の名前や機械などは講義で出てきましたが、実際に行っている様子を見ることができ、とても勉強になりました。薬剤部では医師がオーダーした薬を実際に袋に詰める作業を体験しました。薬の取り間違いを防ぐような工夫がされており、薬剤師さんの仕事の一部を体験でき、有意義なものでした。
午後は訪問診療に同行させていただきました。病院に通うのが難しい患者さんには訪問診療、訪問介護を行っており、患者さんや家族の方の気持ちに寄り添った医療が行われていました。訪問診療では実際に患者さんの診察をさせていただき、とても勉強になりました。自分にとって実際の患者さんを診察するのが初めてだったので、戸惑いもありましたが、貴重な体験となりました。診察を行った後、実際にカルテを書き、医師と同じことができてとてもうれしかったです。
今回の実習を通して地域医療についての理解がとても深まりました。大学病院では学べないことがたくさんあり、地域と連携した医療を体感することが出来ました。高齢化が進む地域での医療の在り方に触れてみて、自分の将来の医師像をしっかりと考えることが出来ました。
このような素晴らしい体験をさせていただき本当にありがとうございました。自分にとってとても有意義な時間を過ごすことが出来ました。
令和元年度実習 新潟大学医学部3年 山谷英里
今回は貴重な経験をさせていただきありがとうございました。午前中に臨床検査、薬剤部、リハビリの見学、午後に訪問診療、病棟回診の経験をさせていただきました。
午前の実習では普段は見られない部門を見学させていただきました。薬剤部では薬の一包化や軟膏の混合などの体験をさせていただきました。外来の時間帯であり、次から次へと処方箋が送られてきており、調剤するために時間が必要であり、患者さんが薬をもらうために時間がかかる理由がわかった気がしました。リハビリでは、患者さんの年齢や地域のニーズに沿ったリハビリ提供がなされていることを知りました。
訪問診療では、病院に通うことのできない患者さんを診察できるというほかに、実際の生活環境がどのようになっているかを知るのにとても効果的だと感じました。さらに医師、看護師と患者本人とそのご家族の信頼関係をみることができました。患者さんのご家族が自身の体調に関することを相談している様子も見られ、地域医療の特徴的な場面だと思いました。お一人お1人の時間をしっかりと確保し、病気以外で困っていることなども気軽に相談できることが最大のメリットだと感じました。一方デメリットとして患者さんのお宅が遠い場合、時間がかかること、また地域の医師自体も少なくまた高齢化しているため訪問診療がどうしても難しい場合があると指導医から聞きました。また実際に内科回診について回ったことで、高齢の患者さんが多いこと、その中でどれだけの治療をするかを家族の意向や状況を踏まえながら判断する必要があることを学びました。寝たきりで認知症が進んでいる患者さんも多く、家族との話し合いが必要だと感じました。
今回の実習で、「地域で治し支える医療」というキーワードをいただきました。今回の実習を通して、一人の患者さんを、その家族や生活状況を含め考え、また自宅に帰すだけでなく、帰った後も見続ける医療展開がなされていると実感しました。このような地域医療の様子を頭に置きながら、今後始まる、臨床の勉強をしていきたいと思います。
実習させていただき、ありがとうございました。